ある日のこと、北大苫小牧演習林から札幌の大学本部に出かけた私は、例によって、二十年来の恩師である太田嘉四夫先生の研究室に顔を出した。
すると先生はちょうど電話に出たところであった。
「エッ、何ですか。キツネの色を聞きたい?」
そこでたちまち、先生一流の単純明快な答えが飛び出した。
「それはキツネ色に焼いたパンの色です」
わからないわけではないが、この答えは論理的に撞着している。別にパンでなくても、なんだってキツネ色に焼けばキツネの色になるわけで、てんで答えになっていない。
だが、どうやら新聞記者らしい相手の人は気を呑まれてしまったのか、それで納得したらしい。むろん、先生もそれで澄ました顔をしているが、私は先生のそういうところにいつもはらはらする。
たしかにキツネの体色はトースターで焼きあげたパンの色に似ている。ただ、北海道のキツネは本州以南のキツネに比べて色が明るくて美しいから、しいて先生の言い方を正すならば、それは焼きすぎないように上手に焼きあげたパンの色、といった方がよさそうである。
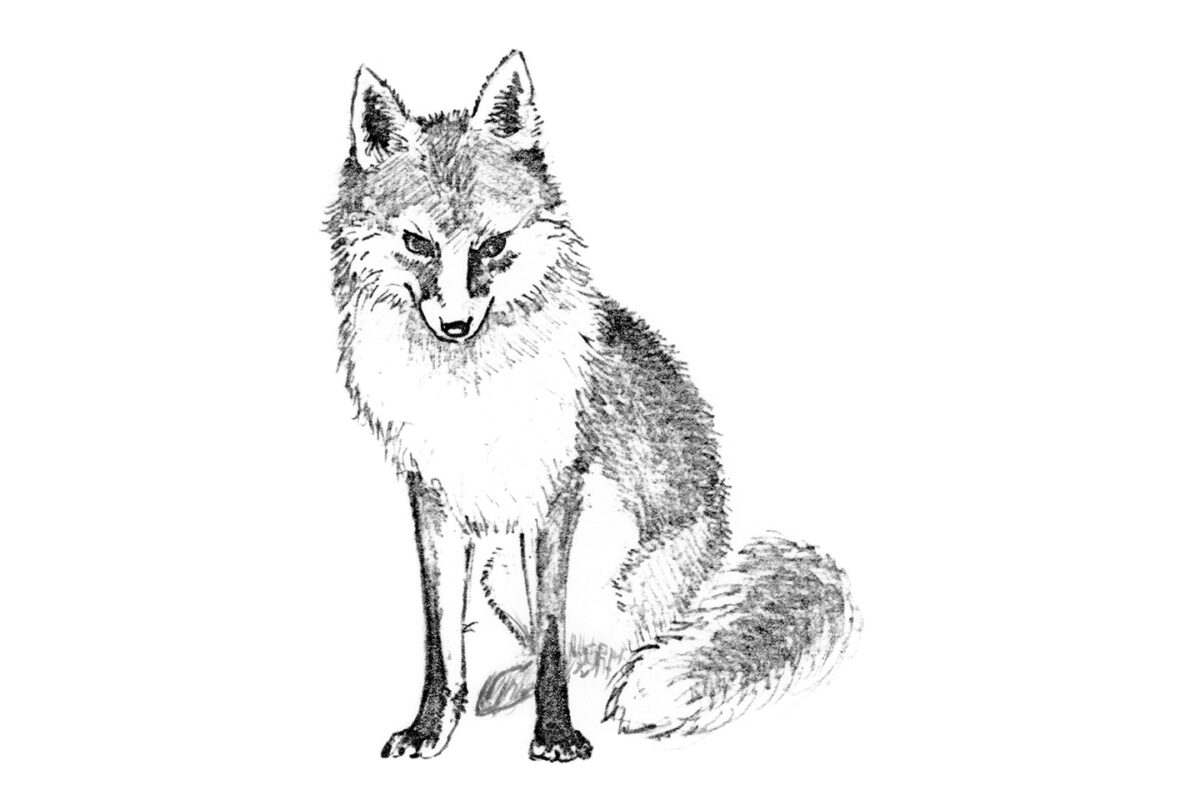
私が北海道の原野で、このキツネ色の動物にはじめて出合ったのは、まだ大学院生だったときのことであった。
当時イワナの研究に没頭していた私は、二月の初旬に、道東の知床半島の近くのイチャニ川という小さな川で調査をしていた。私は重装備で川に浸って、イワナの稚魚を採集していた。名にしおう道東の厳寒期である。日中にもかかわらず、水から取り上げた稚魚はみるみるうちに短い鉛筆のように固く凍ってゆく。しかし、渓流の魚の世界に、何とかしてはいり込みたい一心の私は寒さを忘れて夢中だった。
そのときであった。ふと気がつくと、二〇メートルほど先の雪に閉ざされた森の中に、一頭のキツネがいたのである。
凍てつく寒さの中で、キツネはじっと私を見つめていた。私はこのときのキツネの印象を、今でも忘れることができない。なんという野性的な美しさだったろうか。
赤褐色、というよりも紅色を帯びた黄金色のふかふかとした毛並み、衿から胸元を飾る真白な毛、しなやかな体にバランスを与える太い尾、そして、私を見つめる琥珀色の瞳は燃えるように輝いていた。
流れのなかに立ちつくして思わず見とれていた私は、気をとりなおして写真を撮ろうとし、川岸のザックに手を伸ばしかけた。
すると、赤毛の野生動物の体が一瞬跳躍し、紅色の光芒と化したかと思うとたちまち森の奥深くに姿を消してしまった。瞼の裏に、キツネ色の余韻だけが残った。
ところで、キツネの色はみなキツネ色だろうか。
……
(「キツネの七変化」より/続きは『たぬきの冬』でお楽しみください)

石城謙吉
北海道大学名誉教授。専攻は動物生態学、森林科学。1934年、長野県諏訪市生まれ。北海道大学農学部卒業後、高校教員を経て、同大学院修了(イワナの研究で農学博士)。1973年から23年間、北大苫小牧地方演習林長。同演習林の森林を総合的自然研究の拠点とするとともに、市民と自然の交流の場として開放。著書に『イワナの謎を追う』『森林と人間』『自然は誰のものか』など。


